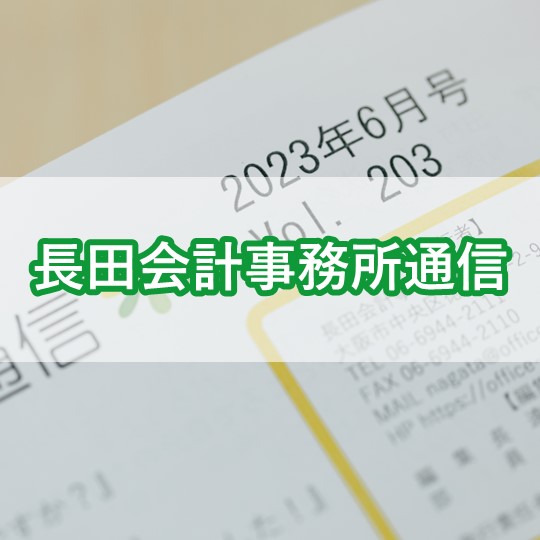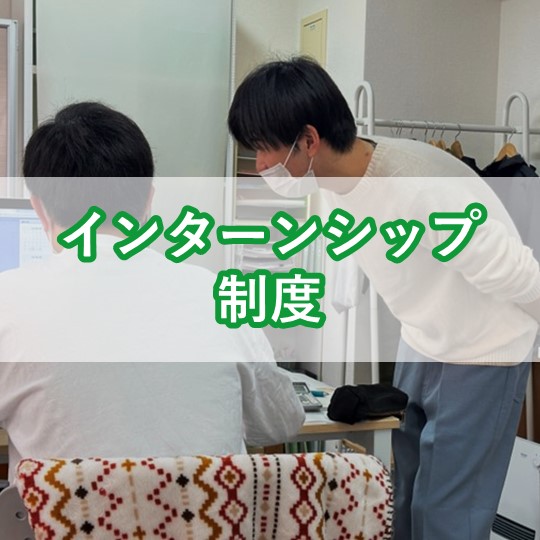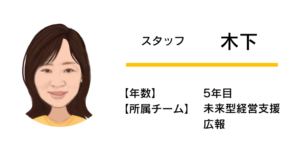
スタッフ木下です。
暖かい日が多くなり、本格的に春が来たのを感じています。
春と言えば、そう! 入学&入社!
私は他のスタッフが確定申告に明け暮れる2~3月の間、採用活動に奔走しておりました。
経営計画立案会議でも人件費計画はかなり時間を割く分野です。
みなさまはどのように採用に取り組まれているでしょうか?
事務所ではSNSを活用してインターン採用に力を入れています。
本記事では、採用広報を担当した木下より、事務所の事例と採用のアイデアをご紹介します!
※長田会計事務所通信vol.225に掲載済の新聞をロングバージョンでお届けします
SNSは採用の可能性を広げる強力なツール!
突然ですが、みなさまはSNSを活用していますか?
事務所では、2014年にFacebook、2021年にInstagram、2022年にYouTubeを開設しました。
普段は事務所の日常を発信し、採用シーズンは募集情報を掲載しています。
事務所は今年、春の採用で「採用予定人数の5倍の応募者数を目指す」という目標を立て、それに対して広報部ではインスタグラムで週2回の動画を投稿するという目標を立てました。
詳しくはコチラ→長田会計事務所のつくりかた⑩「2025年度の経営目標を決定しました!」
継続した投稿は大変ですが、SNSは採用の可能性を大きく広げるツールだからこそ、リソースを割く価値があると考えています。
実際に、歴代のインターン生に応募理由を聞くと、「SNSを見て安心したから」という人が多いです。

順調に応募者数が伸びています!
「昔は求人広告を見て直接応募するのが当たり前だったのに、そんなの要るの?」という声もあるかもしれません。
そのようなジェネレーションギャップがある要因として、現代の若者(Z世代の私がいうのもなんですが)は「失敗したくない」という思いが強く、慎重に情報を集めてから行動する傾向が強いと言われています。
背景には少子化による教育環境の変化や、SNSによる誹謗中傷の可視化などが挙げられています。※「若者 拒否回避志向」で調べてみてください。
そのため、事前に企業の雰囲気をしっかりチェックした上で応募する人が多いです。
SNSの普及も、若者の志向の傾向も、これから先過去に戻ることはなく、むしろより強まって行くと思われます。
若者全員がみんな失敗を恐れているというわけではないですが、SNSのチェックは自然なことという印象です。
大企業でなくても、SNSで企業の魅力を伝えることはできる!
SNSが普及し続ける時代において、企業がこれを活用しない手はありません。しかも始めるのにお金はかかりません。
「SNSで採用活動?」と冗談のように思われるかもしれませんが、これはいたって真面目な手段です。
内容についても、文字情報だけよりも、画像、そして動画のほうが伝わる情報量は圧倒的に多いです。写真と実際に会った印象が違ったということがあるように、動画なら話し方や雰囲気で文化まで伝えることができます。SNSを活用していない中小企業の求人は、まるで「扉を少し開けて、隙間から手招きしている」ようなもの。SNSを活用することで、その扉を大きく開き、より多くの求職者に企業の魅力を伝えることができます。
ただ、効果が高いからといって、最初から動画に挑戦するとハードルが高くなってしまいます。
手軽にいつもの日々の少し面白かったことを写真に撮り、時々アップするのがオススメです。
事務所ではイベントの様子だけではなく、普段の日常の様子を上げています。毎日でなくとも、最初は2週間に1度の更新でも十分です。
ちなみに、私が入社前に見た投稿で一番印象に残っているのは「スタッフの服(ボーダー)が被った」というものでした(笑)

2018年の遠藤さんと小向さんです(笑)
手軽に、背伸びしないで続けるのが一番だと思います。
インターンシップは「長期の面接」
正社員雇用において、ミスマッチは避けたいものです。
インターンシップは、企業と求職者がお互いを知る「長期の面接」とも言えます。
かく言う私も元インターンシップ生の一人です。
正社員として入社する前にスタッフの人柄を知ることができる点や、仕事を知ることができる点は大きな魅力です。
いきなり正社員雇用となると、企業も求職者もハードルが高いものですが、まずは短期の雇用でお互いを理解し、その後長期の雇用契約を結ぶというスタイルは今後の中小企業の採用において大きな可能性を秘めています。
そして、その役目を担うのが「SNS」と「インターンシップ」だと考えています。
最近お客様から聞いたスキマバイトアプリ「シェアフル」も、基本的には短期の契約ですが、良い方が来たら長期雇用可能なのだそうです。
柔軟な雇用形態が求められる時代なのかもしれません。
「インターンシップを始めてみようかな」と思われたら、コンサルタントに相談してみるという手段もあります。
2020年代入社の私でさえ、最近の就活については状況が変化しすぎていて把握しきれません。
実は今回の募集もコンサルタントに相談しました。
以前に比べて初動の反応が思わしくなく、「もしかしてインターン市場はもう終わってしまったのか?」と焦りましたが、相談の結果、実際には全く逆の状況だと分かりました。
今では「インターンシップ」という言葉が特別なものではなくなり、学生さんたちも気軽に応募するようになっているそうです。
情報を収集しながら冷静に対策を更新していった結果、その後は順調に応募者が増えていきました。
情報をアップデートするには、その分野についていつも高い関心を持って関わっている専門家の力を借りるのがベストです。
よろしければ2025年春採用に向け投稿した動画もご覧ください。
いつも以上に力が入って長くなってしまいました。
若手の採用・教育にお悩みの方へ、若手世代である私だからこそ、お伝えできることがあるかもしれません。
(すでに学生さんとジェネレーションギャップを感じてはいますが…(笑))
ご参考になれば幸いです。
以上、スタッフ木下でした!


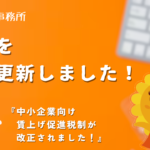
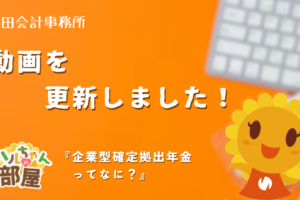
-300x200.png)

-300x200.jpg)

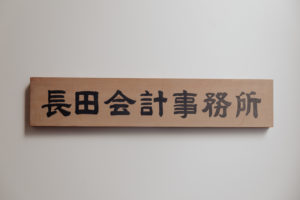
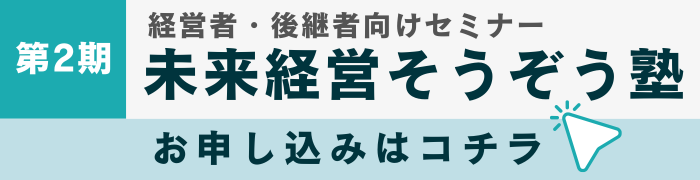
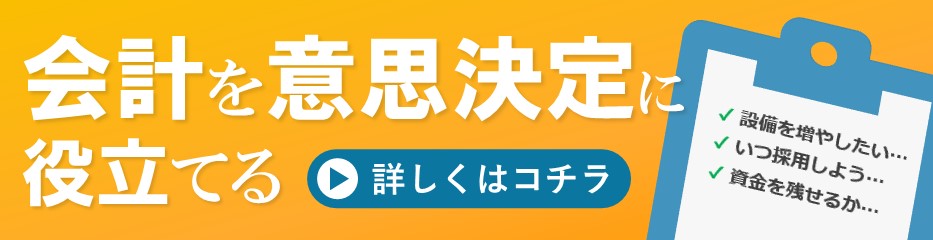
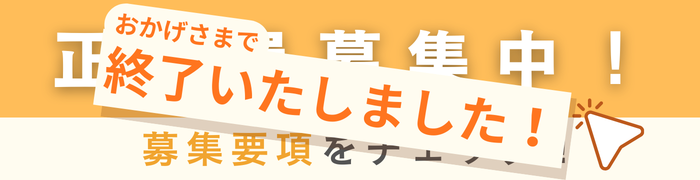
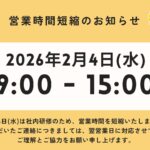

-150x150.jpg)